新着先生一覧

K先生
なし~8000
在学 岐阜大学
男性
初めまして。
医学部医学科在学中の大学生講師です。現在、個人契約や大手家庭教師会社、医学部専門予備校個別オンラインにて家庭教師講師をしています。
学生認定講師です。
体育の家庭教師講師も行っています。
何でもいいから医学部に入れてくれという方がいらっしゃいましたら、週数学4時間物理化学2時間ずつ確保して下さればご対応致します。
都内の大学工学部で特に生命現象に関わる化学を学んでいましたが受験勉強を同時進行で進め、中途退学そのまま医師になる為医学科に進学しました。
前大学の頃より教育のお仕事に就き、これまでの指導経験や私自身の受験経験を踏まえ、基礎的な問題から発展的な問題の指導もお任せください。
希望時給は、5000〜30000ですがご気軽にご相談下さい。対応致します。
オファーお待ちしております。

けい
なし~5000
卒業 追手門学院大学
男性
はじめまして!
国語、社会がメインです。
授業はとにかく楽しく!を目指しています。
生徒が明るくなった、授業が楽しみと言っていただける生徒様も多いです!
また接客業の代表を7年していた事もあり、
人との接し方なども勉強と交えて教えていきたいです。
中学受験も経験済みです。
僕は勉強を始めたのが高校3年生からと遅かったですが
猛勉強の末、現役でセンター入試の現代文は98%取ることができました!
この経験を活かして効率的な勉強方法も独自に考えております!

ayano
なし~10000
卒業 慶應義塾大学
女性
都内でプロ家庭教師として活動しております。
中学受験対策と内部進学フォローがメインですが、
「お子さんにとって良い環境はどのようなものなのか」
「そのために今私自身がどのように関わるべきなのか」
という点を常に考えながら日々の学習やメンタル面の成長をご家族と一緒に見守りつつ、リードしていくスタイルを大切にしています。
単に学習面のみを担うのではなく、お子さんを含むご家族の関係性やメンタル面のフォローもトータルで目が行き届くように心がけております。
私自身が子供の頃から勉強もそれ以外の趣味や習い事もメリハリを付けて楽しみながら受験や進学をして来た経験がございますので、心と体と頭がバランス良く・またそのお子さんにとってしかるべきタイミングで育っていくように接しています。
また私自身の両親以外の多くの方々に「育てて頂いた」感覚が人生においても非常に励みになっておりますので、私も関わらせて頂くご家庭の皆さんにとってそういった存在で在れるようにとの思いでお仕事を続けさせて頂いております。
基本的には長期のお客様がほとんどですが、短期でのご依頼やご家族の別荘・海外など遠方への帯同も承っておりますのでどうぞご相談ください。
<指導方針>※中学受験の場合
①低学年のお子さん
⇒受験のための勉強や通塾が本格化する前に、お子さんの特性を見極めつつ「思考するための素地作り」と「集中力・作業処理スピードの向上」や「信頼関係の構築」をじっくり進めていきます。
(学年が上がり塾などでの拘束時間が増えてからは、知識のインプットアウトプットと問題の処理に時間を割かなければならなくなるため)
※もちろん上記の3要件が比較的高い状態で備わっているお子さんの場合は早い段階でより発展的な思考や議論へ導いていきます。
②高学年のお子さん
⇒この時点では何かしらの問題点が明確化している可能性が高いため、その原因を把握したうえで志望校やゴールへ向けた道筋を考え(要するに勝ち方を考えるという事です)推進していきます。
<略歴>
幼い頃より人の「心」というものに興味があり、「心の処方箋」や「こころ(夏目漱石)」など精神面の描写が豊かな本を読んでは分析する不思議な子供でした。また犬好きが高じて、海外の動物番組を夜な夜な見て試行錯誤しながら当時飼っていた愛犬を訓練して一緒に競技会に出ていました。
学生時代は馬術に打ち込み、競技で入賞するべく日々鍛錬。
新卒でコンサルティングファームに就職した後、コーチング国際資格を取得・HR領域のコンサルティングと併せて経営者コーチングや幹部研修などを実施。
その後学生時代から続けていたプロ家庭教師として独立。

けん
なし~3500
卒業 大阪府立東高校(4月より同志社大学)
男性
私が英語学習を本格的に始めたキッカケは、英語学習動画を投稿しているとある配信者の英語力の高さ・並々ならぬ努力に感銘を受けて、英語の世界にどっぷりハマりました。
私は、もともと中学校の英語の定期テストで、50点台を取り続けていて、まさか将来、英語の家庭教師をするなど夢にもみていませんでしたが、その配信者に巡り合ってから、「この人みたいに英語ペラペラになりたい」と奮起し、英語を自主的に勉強し始めました。
英語のみならず、全てのことに当てはまると思いますが、何か1つのことに熱中するキッカケは案外、些細なことから始まると考えています。なので、生徒様にとって、私が英語を得意・好きになるキッカケになれるよう心がけてまいります。
私の授業では、入試・定期対策はもちろん、英語そのものを好きになって頂けるように、英語の歴史や単語の語源などの話も授業に織り込んでいこうと考えています。
英語指導に関してまして、英語をただの暗記科目で終わらせず、”頭を使って”理解することを意識した授業を展開してまいりますので、そのような授業をお探しの方はぜひご受講くださいませ。

みみ
なし~1500
在学 上智大学
女性
こんにちは

みそ
なし~3000
在学 九州大学
男性
勉強が苦手な子の指導経験を活かして、生徒に寄り添う努力をします。

りょう
なし~3000
卒業 群馬大学
女性
今までさまざまなタイプの学生さんと勉強をしてきましたが多くの生徒さんに満足していただけていたと思います。も最も意識していることは、お子様に寄り添った柔軟な指導をすることです。毎回同じ時間に同じ場所で勉強をすることがつまらないのであれば、やり方や場所を変えながら行いますし、やる気にムラがあるのであればこまめに休みながらの指導を行います。日によって、お子様によって適切なアプローチがあると考えているため、その子にあったやり方を模索させていただきます。
責任感は強いです。お任せいただいたからにはお願いして良かったと思っていただけるよう努めさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
オフラインの方がやりやすさはありますが、場合によってはオンラインも対応できますのでお気軽にご相談ください。

ユウ
なし~3000
在学 ルーテル学院大学
女性
【自己PR】
小中高ともに最高偏差値は75で、国語は高校記述式模試で全国25位を取った経験もあります。小論文や作文などの記述が得意です。読書量が多く、多いときは月100冊以上読んだ時期もあるほど本が好きです。小学生の塾入学時は45程度だった偏差値が最高偏差値80まで伸びた経験があります。
勉強が楽しいと思えるようになってから急激に成績や学力が上がっていきました。学校の暗記による教育に疑問を持ち、方程式の原理を理解することの大切さや、ただ暗記するだけでは覚えたとは言わない、という意識を持ってしまったため、暗記で詰め込み教育をしていた中学、高校での勉強はあまりしませんでした。その経験を活かし、どうしてそうなるのかを自分で説明できるような教え方をしていこうと思っています。
自分自身、あまり厳しい指導は得意ではないとわかっているため、厳しいスパルタでの指導を希望される方は合わないかと思われます。
もし課題が終わっていなくてもあまり怒りませんし、できないところがあっても前回やったところがなぜわからないのかなどと理不尽に叱ることもありません。甘やかし過ぎな気もしますが、そもそも大半の生徒にとって勉強自体が大変なものだと思っているので、勉強のハードルを上げたくないというのが私の思いです。
怒られたり叱られたりしながら勉強をするよりも楽しく面白く勉強ができたほうが勉強をするモチベーションになると思っております。
もし指導をさせていただけるのでしたら理解し学ぶことの楽しさを感じられるような授業をしていきたいと思っております。
【指導例】
・算数、数学の場合
一単元を一通りマンツーマンで指導したあと、課題や授業内での躓きから苦手な部分を重点的に指導します。
指導時には生徒がしっかり問題の解き方を理解しているかどうか、その都度自分で説明してもらいます。
その後、単元のまとめテストを行い、間違えた箇所からどこが苦手な部分かを再度炙りだし、集中的に解説を行い、その分野のテストでケアレスミス以外の要因での間違いがなくなった時点で次の単元に進みます。
・英語の場合
まず英語における重要な品詞と五文型の理解から始めさせていただきます。
その後五文型の各解説を行い、英文がどういう成り立ちで出来ているのか、単語同士がどのような関係になっているのかを一人で説明できるようになるまで指導いたします。
現在分詞、過去分詞、不定詞、関係詞の解説を行った後、実践的な長文読解の指導に入らせていただきます。

ヒギンズ
なし~6000
卒業 名古屋大学
男性
高校生・大学受験生への基礎科目の指導はもとより、大学生・高専生・短大生等への単位取得のための補習指導、大学院入試に係る専門科目の指導、高専生の大学編入に関係する基礎科目の指導、さらには社会人の方のニーズに応じた指導等につきまして、幅広く担当させて頂いています。
元国立大学大学院理学系教授としての長年の教育経験を活かした理工系分野の基礎全般に渡る指導、特に数学(線形代数、微積分学、微分方程式、複素解析、ベクトル解析等)、物理学(力学、電磁気学、量子力学、熱力学、統計力学、物性物理学等)、さらには工学(機械力学、電気回路、半導体工学、量子工学等)の各分野の指導が可能です。高校生・大学受験生への数学および英語の指導も行っています。
大学研究室所属の100名近い学生・院生の輩出経験で培った分かりやすくフレンドリーな指導がモットーです。ZoomやSkypeを用いたオンラインでの指導により、国内はもとより、全世界の皆さんを支援させて頂きます。ご質問、ご要望等なんでもお伺いしますので、お気軽にコンタクトしてください。

ひろ
なし~6000
卒業 文教大学
男性
プロフィールご覧いただきありがとうございます!
私は現在、家庭教師を専門に小学生から社会人まで様々な方のサポートをしています。
教科指導も当然行っていますが、基本的にはそれぞれの目標ややるべきことを整理し、普段の取り組み方から見直していくことが自分の役割だと思っています。
基本的には褒めて伸ばすタイプの指導をしていますが、約束したことを守れなかった時はなぜ出来なかったのかははっきりさせていきます。
勉強するべき本人が誤魔化して中途半端にこなすクセを付けてしまったら、信頼関係も築けず目標にも到達出来にくくなるためです。
仲良くなることは大前提として、成長や自己実現を目指して約束したことを守れる人間関係を作り上げるようベストを尽くしたいと思います。
私自身まだまだ未熟者で先生と呼ばれるほどのものは持ち合わせてないですが、子どもたちの成長の一助になれるよう頑張ります。
宜しくお願い致します!

銀
なし~6000
卒業 明治大学
男性
現在、家庭教師にて8家庭ほど担当しており、大手塾(サピックス、四谷、早稲アカ、日能研)に通われている生徒を中心に指導しております。
六年生は男子1名、女子3名
現在の指導例
サピ5年生男子→中堅クラスにて偏差値50
から62
日能研6年生男子→中堅クラスにて偏差値
58から70
宿題の選別をしつつ、過去問は優先順位や
取捨選択をして本番に取れるよう備えます
ホワイトボードを持参しますので、途中
式の過程はもちろん、本人の理解度を見
ながら授業が進められます。
自身が数学科出身なので、受験は勿論
先を見据えた指導を行なっております。
理科では良く出る暗記ポイント、計算まで
指導致します。
週ごとに何をすべきかのスケジュール管理
等を組み立てて効率良く進められるよう促
し、合格への最短ルートを導きます。
※各ご家庭に、毎回の授業内容や宿題を書
いたファイルでその都度管理しております
4教科全てを見てその都度の勉強法など
をアドバイスし、ご家庭のお悩みを少し
でも共有できるよう、可能な限り面談を
行っております。
※他のご家庭とオンラインにて定期的に目
標発表や、激励会等をして皆さんで切磋琢
磨する環境です。
2023年度5名による実績→法二、明大中野、城北、都市大、栄東、大宮開成、青陵など。
2022年度5名による実績→栄東東大特待3
名、麻布、フェリス、早稲田、恵泉、逗子
開成、市川、青山横浜英和、鎌学など。
様々なご希望のご家庭を担当しております

Chichi
なし~4000
卒業 Kanda University of International Studies
女性
『はじめまして、外国語講師のChichiと申します!』
''楽しくリラックスして、自由な気持ちで、自然に身につくレッスンです。アカデミックな学習・試験対策・学校などの予習復習補習から、文化や必要に応じて歌や漫画など互いに興味が合うものを用いたオリジナルなものまで、大変柔軟な内容が可能で、持ち込みとテキストはもちろん、その他様々なテキストから生徒さんに合うものを用いたり、時には好きな話をしたり、わかりやすく、また、時に英語、フランス語、日本語、など交えたり、同時に複数の言語も教えられます。英語とフランス語を同時に身につけたい方にもおすすめです。
ぜひ、お会いできることを楽しみにしております!!''
【担当】英語、フランス語、日本語、芸術(絵)
【経歴】1999 神田外語大学外国語学部英米語学科卒業 (言語学専攻)
その後、翻訳会社へ入り、その後は多数の大手の塾・予備校、英会話スクール、家庭教師を25年経て、現在個人レッスンをメインに教えています。英語やフランス語、そして日本語の翻訳などもしつつ、プロの芸術家・画家として、国内外で活動しています。
【資格など】TOEIC850, DELF B2, フランス語検定準一級、NHK英会話出演、画家としての受賞・展示歴多数、など。
【特徴】1 楽しくわかりやすく、または、厳しく、と、柔軟です。
2 レベル問わず、本当に何もわからない初心者の方・英語が苦手な方・逆にもっと伸ばしたい方・好きなのになかなか伸び悩んでいる方、大歓迎です。また、予備校経験が長い為、学校の補習・大学入試・資格試験などの対策も任せてください。
3 画家で海外特にヨーロッパの経験を持ち、そのような話や知識も交えて面白い内容です。
4 英会話・文法をやり直したい・今まで習ったのに使えていない文法と結びつけて使える英語を身につけたい・読み書きもできるようになりたい、方にも、おすすめです。文法教授については、大変得意としていますし、一番わかりやすく指導いたします。読解力もお任せください。文法解説をしっかりしながら、しっかり身につけていきましょう!
【内容】1 英語、フランス語 (会話・文法・読み書き・試験対策・学校の補修・旅行会話・歌・その他・英仏混合レッスン)
※まずは気軽にご相談下さい!
2 日本語 (英語やフランス語でナチュラルな日本語を学ぼう!)
3 アート (絵、イラスト、歌)

しょーご
なし~1500
在学 大同大学
男性
高校教員免許取得を考えています!
誰よりも分かりやすく楽しい授業をしていきます!

まと
なし~3000
在学 慶應義塾大学
男性
選んでくださったら、全力でサポートさせていただきます!よろしくお願いいたします

タナカ
なし~2500
在学 自治医科大学
女性
担当させて頂いていた生徒さんが無事志望高校に合格されたため、新しい生徒さんを探そうと登録しました。英検や小学校〜大学受験全てを経験しておりますので様々な面でお力になれたらと思っています。よろしくお願い致します。

pakipaki
なし~4000
卒業 千葉工業大学
男性
こんにちは。前川将吾と申します。淡路島の個人塾で講師をしています。
普段から個別指導をしていますので、オンライン指導も任せて下さい!!
兵庫県の公立高校の受験にも対応していますので、ご相談などあれば是非お話し下さい。
面白くて楽しくて、でも真面目に勉強を取り組んでいければ幸いです。
よろしくお願いします。

ともき
なし~5000
在学 佐賀大
男性
指導にあたってはまず家庭、生徒さんとの信頼をきづいていくことが必要です。勉強だけおしえていけばいいという考えではなく色々な話もしながらモチベーションを下げることなく勉強を進めていきたいと考えています。
指導は十分に理解してもらうことを第一として個人にあった指導を心がけています。
また部活もしているので効率よく勉強をする方法なども教えることが出来ます。

ゆうた
なし~5000
在学 筑波大学大学院(大阪大学 卒業)
男性
詳しい指導方針は以下サイトをご覧ください!
https://yuta-tutor.notion.site/2307315dfb7f80ac9cfdc58e22f92564
(当URL添付はSENSE8の許可を得ております。)
勉強を教える「先生」というよりも、成績向上のための「伴走者」が私の目指す講師像です。生徒さんが着実な成功体験を積み重ねモチベーションを高められるように全力でサポートいたします。当方は英語学・認知言語学を専門とする大学院生の講師で家庭教師は今年度で5年目です。
「指導可能教科」に記載した教科にはそれぞれレベル別(基礎〜入試レベルまで)の独自カリキュラムを持っているため、塾の代用としてご活用いただくことができます。
学校の補習としてご活用いただく場合は、学校で使用している教材に準拠した授業を行います。
ご希望に応じて独自カリキュラムと学校補習を組み合わせてご利用いただくことも可能です。カリキュラム編成についてはそれぞれの生徒さんのニーズに合わせて柔軟に行っております。
各教科の私の指導の方針についてご案内いたします。
【英語】
大学の専攻は英語学・言語学です。英文法・語法における日本語との差異を理解し、英語の「謎解き」を楽しみながら生徒さんと学べていけたらと思っています。受験生は受験の要とも言える英語を確かな得点源にするために、知識・技能を確実に定着させ、文章の論旨を正確・的確に把握することを目標にします。また非受験学年(中学1〜2年、高校1〜2年)は英語に対する抵抗感を払拭し、実践に活かせる英語力を身につけることを目標とします。
英語の授業は大きく分けて以下の4つに分かれています。
① 英文法・語法
私の大学の専攻は英語学・言語学です。英文法・語法における日本語との差異を理解し、英語の「謎解き」を楽しみながら学べていけたらと思っています。暗記をしなければならない部分は覚えていただきますが、文法論理から丁寧に説明いたしますので暗記量は一般的な授業よりも少しは減らせるかと思います。初期の基礎レベルでは文法の授業を重視し、読解に活かせる文法を学んでいただきます。
文法論理の学習には「なぜそうなるのか」を理解するプロセスを大切にしています。例えば、なぜ現在完了形が「過去から現在までの継続」を表すのか、なぜ関係代名詞は文と文をつなげる役割を持つのかを論理的に解説し、イメージを持ちながら学んでもらいます。単に形だけを覚えるのではなく、背景にある理論を理解することで、暗記に頼らずとも自然に使えるようになります。もちろん、英語の学習には覚えるべき単語や表現も多く存在しますが、文法の論理をしっかり理解していれば、単なる丸暗記に比べて格段に記憶の定着が良くなります。これにより、学習者が苦手意識を持ちがちな文法の部分も、納得感を持って学べるようになります。
② 英文解釈・長文読解
各講の文法・読解テーマに沿った英文の精読・和訳を通し、英文の基本構造とその内容を把握・理解する基礎的英文読解力の向上を図ります。文全体の意味やコンテクストを踏まえ適語適訳する力を養い英文を正確に理解するスキルを構築を目指します。文法・読解テーマに沿った英文の精読・和訳を通して、英文の構造と内容を把握する力を養います。単語の意味を拾い読みするのではなく、英文の主語・動詞・目的語・修飾語の役割を正確に理解することを重視しています。特に、関係代名詞や倒置、時制の一致など受験頻出の構文を分析し、一文ずつ丁寧に解釈します。和訳演習では、直訳ではなく、論理やニュアンスを正確に日本語に表現する力を養い、自然な日本語に訳し直します。複数の節が絡み合った長文も、論理構造を視覚的に整理し、全体の流れを理解する訓練を行います。
③ 英作文
日本語と英語の言語的な構造や表現の違いをしっかりと理解しながら、正確で自然な英文が書けるように丁寧に指導を行います。日本語と英語では、主語や述語の配置、修飾語の位置、時制の扱い方など、文章の組み立て方に多くの違いがあります。例えば、日本語では主語を省略することが多いですが、英語では主語が明示されなければ文として成立しません。また、英語では主語→動詞→目的語の順で明確に並びますが、日本語は比較的自由な語順を持ち、文脈に依存することが多いです。このような違いを理解した上で、英語らしい論理的な文章の組み立て方を学んでいきます。添削・フィードバックをこまめにを行い、誤りの確認と改善案を具体的に示します。また、基本的な文型や複雑な表現も学び、場面に応じた使い分けができる力を身につけます。フィードバックを通じて、論理的で伝わりやすい文章を書くスキルを確実に定着させていきます。
④ 志望校対策英語・資格試験対策英語
上記で身につけたスキルをもとに、本番の試験形式に合わせた問題演習を行います。過去問を中心に、出題傾向を分析した予想問題も取り入れ、実際の出題形式や設問の難易度に慣れ、本番さながらの練習を積みます。
問題を解くだけではなく、解法のプロセスも確認し、長文読解では精読とスキャニングの技術の使い分けを取り入れ、時間内に正確な解答ができるように指導します。演習後には徹底した復習を行い、誤りの原因を分析して次に生かします。また、添削指導を通じて、不自然な表現の修正や論理的な構造の改善を行い、試験本番で確実な得点ができる力を身につけていきます。
▼ 長文英語・英文解釈(英文和訳型)の授業の様子
https://literatura-nakano.blogspot.com/2021/08/blog-post.html
▼ 英文法・語法の授業の様子
https://literatura-nakano.blogspot.com/2021/08/blog-post_6.html
▼ 英作文の授業の様子
https://literatura-nakano.blogspot.com/2021/08/blog-post_23.html
▼ 特定大英語(志望校別対策講座)の授業の様子
https://literatura-nakano.blogspot.com/2022/04/blog-post.html
【数学(算数)】
私は、単に公式にあてはめたり、定理を暗記してそれを機械的に使うといった従来型の学習スタイルから一歩踏み出し、生徒一人ひとりが「なぜそうなるのか」を深く理解しながら学んでいく姿勢を大切にしています。目先の得点やパターン演習に偏りすぎず、数学という教科が本来持つ論理性や抽象性、構造的な美しさに触れながら、数理的な本質に迫るような思考力を育てることを第一の目標としています。
具体的には、「一般化」や「抽象化」といった、いわゆる数学的なものの見方・考え方を身につけることに重点を置きます。これは、単に答えを出すことにとどまらず、問題の背景にある概念や構造に目を向けるという学習態度を養うことに他なりません。教科書や問題集の内容を出発点としつつ、それらを単なる“やるべき問題の羅列”として扱うのではなく、一つひとつの操作や定理の背後にどのような論理や意味があるのかを明らかにしながら進めていきます。
こうした視点で学んでいくと、生徒は目新しい形式の問題や応用的な問いにも柔軟に対応できるようになっていきます。たとえば、数値が複雑であっても、あるいは問題設定が見慣れないものであっても、表面的な情報に翻弄されることなく、「この問題はどのような構造に基づいているのか」「既習の内容とどのように関連づけられるのか」といった観点からアプローチする力が自然と身についていきます。これは受験や定期試験における応用力・思考力を高めるだけでなく、長期的にはあらゆる学問や実生活の場面で役立つ汎用的な知的スキルにつながるものだと考えています。
また、私が特に重視しているのが、「自分が行っている操作や考え方を、他人にわかるように言葉で説明できる力」の育成です。これは単なるアウトプットの練習にとどまらず、自分の思考を言語化することで、頭の中で漠然としていた理解を明確にし、自身の誤解や曖昧さに自ら気づくための極めて有効な方法です。授業中には「なぜそう考えたの?」「この式変形の意味は何?」といった問いかけを重ね、生徒が自分の言葉で説明できるようになるまで丁寧にサポートしていきます。
このように、知識の詰め込みではなく、本質的な理解と思考力の育成を通して、生徒が一問一答の枠を越えた深い学びを実感できることを目指しています。そして最終的には、生徒自身が自ら問いを立て、自ら考え、自ら学ぶ「自立的な学習者」として成長していけるよう、長期的な視点で指導にあたっています。
▼ 数学の授業の様子
https://literatura-nakano.blogspot.com/2021/08/blog-post_29.html
【国語(現代文・古文・漢文)】
国語の指導にあたっては、生徒一人ひとりの理解度や課題に寄り添い、論理的な読解力と確実な得点力の両面をバランスよく伸ばすことを目標としています。本文の主張・展開を的確に把握し、かつ類似・反復構造を見抜く力を養成することが目標です。記述問題では「なぜこの要素が必要で、この要素は不必要なのか」、選択型客観問題では「なぜこの選択肢は誤りで、別の選択肢が正しいのか」を生徒さんと議論して問題への理解を深めていきたいと思います。
論理的な読解眼と着実な解答力の両方を伸ばすべく、講義と演習解説を組み合わせた授業を展開していきます。単なるテクニックのみの解答法に頼らず、読解のために必要な知識や教養を定着させ、大学入試のみならず、それ以降のご自身の学びに生きる国語力を養成することが目的です。授業では、解説中心の講義と実践的な演習を組み合わせ、知識の定着と応用力の養成を図ります。
現代文の指導では、単なる解法テクニックに依存せず、文章全体の構造や論理展開、筆者の主張の把握に重点を置いています。文章の展開に使われるロジックを学び、論理的思考力・読解力を養うことで、言語の処理・表現能力の向上を図ります。また、時事問題や文学、歴史、哲学など幅広い分野の背景知識や教養を取り入れることで、文章をより深く読み解く力を養います。こうした知識は受験対策にとどまらず、受験後の学びや人生においても生きる「本物の国語力」となります。独自に作成した「現代文マニュアル読解法編」「背景知識・教養編」といったカリキュラムを用い、生徒さんが自己流の読み方から脱却し、確実に点数を取れる解答法を身につけられるようサポートしています。
古文・漢文の学習では、単なる語彙や文法の暗記に留まらず、物語や和歌が生み出された時代背景や登場人物の価値観、さらに当時の生活習慣など、幅広い背景知識や教養を重視した指導を行っています。
これにより、文章の内容がより深く理解できるだけでなく、根拠に基づいた正確な読解力や設問に対する解答力が自然と養われていきます。さらに、歴史的な背景を知ることで、古文・漢文の世界が現代との対比の中でより身近に感じられ、興味を持って学べるようになります。授業では、基礎から丁寧に指導を行い、苦手意識の克服を目指すとともに、定期試験や大学入試での得点力向上を実現します。また、生徒一人ひとりの理解度に合わせた個別指導を心掛け、着実な学力定着を図ります。最終的には、古文・漢文の学習を通じて、文学史に対する理解を深めると同時に、論理的な読解力や表現力の向上も目指していきます。こうした総合的な学びを通じて、生徒が自信を持って文章に向き合えるよう、全力でサポートしていきます。
▼ 現代文の授業の様子
https://literatura-nakano.blogspot.com/2021/08/blog-post_45.html
▼ 古典(古文)の授業の様子
https://literatura-nakano.blogspot.com/2021/08/blog-post_55.html
【社会科・地理歴史 公民】
社会科・地理歴史公民は受験において努力が着実に反映される科目です。特に歴史科目に関しては縦(時代)のストーリーのつながりと横(政治・外交・社会経済・文化)のひろがりが理解できた時の感動を共に味わいたいと思います。
日本史は私の高校時代の得意科目でもありました。日本史の実力を伸ばすために、一問一答の使い方や、問題演習のやり方などをレクチャーしていきます。正しい努力で着実に得点力を伸ばしていきましょう。日本史は土地制度や経済史をはじめ論理的な思考能力も求められる科目です(だからこそ、日本史は面白いのですが...)。そのストーリーをロジカルに解説し、納得して理解していただくことが私の役割の1つかと考えます。私は大学の授業で日本史学の授業を履修していました。古代史研究の最前線で活躍される授業担当の先生のお話を聞いて思ったことは日本史の醍醐味は「暗記」ではないということです。史料・資料のコンテクストから史実やそれに関わる人物の意図、また時期区分を読み解くといった「思考」が求められる学問です。果たしてなぜ私たちは歴史を勉強するのか、その答えは私の授業の中で明らかになります。
地理については系統地理と地誌をそれぞれ体系的に指導いたします。地理の学習のポイントは知識を深めることも当然大切になってきますが、資料や図表などを読み解く思考力も重要になってきます。現象や事象について「なぜこのようなことが起こっているのか」ということをとことん考え、しっかりと説明できるようにトレーニングしていくことで地理の力を伸ばしていきます。
公民(現代社会・倫理・政治経済・公共)は現代社会の複雑な構造や価値観、政治や経済の仕組みを理解する力を養います。特に現代社会・政治経済では、日本や世界の政治制度、経済構造の成り立ちや仕組みを学び、現代社会の動向を読み解く視点を育てます。また、倫理では社会問題や人間の生き方に関する多様な思想を学びます。公民・公共の学習は、ただ知識を暗記するだけでなく、社会の出来事を多角的に捉え、自らの意見を論理的に表現する力を身につけることが重要です。時事問題やニュースを通じて実践的な理解を深め、社会の動きに敏感な思考力を養成します。これにより、公民分野の得点力を着実に向上させます。
※ 難関国公立大学で主に出題される論述型や、私立大学で主に出題される正誤・客観問題や空欄補充型に広く対応します。
※ 大学受験生は、ご希望に応じて受験の科目への優先順位に合わせた指導ができます。(共通テストしか利用しない場合〜2次試験・私大の選択科目として利用する場合まで)
▼ 日本史の授業の様子
https://literatura-nakano.blogspot.com/2021/08/blog-post_37.html
【理科】
理科の指導においては、単なる用語の暗記や公式の機械的な適用にとどまらず、「なぜそうなるのか」「どうしてそのように考えるのか」といった因果関係や原理の理解に重点を置いて指導を行います。理科は本来、自然現象を論理的にとらえ、それを再現・予測するための学問です。ですから、目の前の現象や実験結果を観察し、自分の言葉で説明する力を養うことが、深い理解につながると考えています。
具体的には、教科書や問題集をベースにしつつ、現象の背後にある仕組みや法則に注目して学習を進めていきます。また、生徒が自分の考えを言葉にして説明できるようにすることも重視しています。自分の言葉で説明することは、理解を確認するうえで最も確実な方法の一つですし、定期テストや入試における記述問題への対応力にもつながります。知識を「知っている」だけでなく、「使いこなせる」状態にしていくことが、理科の学力向上の鍵だと考えています。
【小論文】
小論文は一見、対策のしにくい科目ですが、正しく対策をすれば、周囲と大きく差をつけることができます。最初は、論理・背景知識(主に、課題型小論文・難関大学現代文必須テーマから)の講義を行い、徐々に実戦演習に移行するという形です。
受験だけではなくて大学入学後にも活きるような学びをしてもらいたいと考えています。当然ながら演習後は添削の上フィードバックを行っています。
▼ 小論文(現代文でも同じ内容を扱う授業があります)の授業の様子
https://literatura-nakano.blogspot.com/2021/09/blog-post_22.html
また「学習」そのものの姿勢について(学習計画の立て方や学習習慣の付け方)についてもアドバイスも行っております。
例えば学習計画・実行記録をお渡しし、私が確認、管理・アドバイスを行っています。(はじめは計画表の立て方から細かく指導し、次第に自分で課題を発見し学習計画が立てられるようになるまで指導します)
オンライン指導をご希望の方は、ZOOMやスカイプ、LINE通話等を利用する形での授業も可能です。
【授業のポイント】
・生徒さんの集中力がどのくらい続くかを把握した上で、適宜休憩や雑談を入れ、学習が長続きするように工夫します。また、授業するお話には生徒さんの興味や関心を引きつけるような話題を盛り込み、生徒さんの好奇心を高めます。
・「ペースを決めて復習に重きをおくこと」「複数回復習を繰り返すこと」を大切にしながら学習を進めています。人間の記憶は1日単位でおおよそ半減するという法則(エビングハウスの忘却曲線)があります。しかし人間の脳は繰り返し見たり聞いたりしたことは記憶に残りやすいという傾向がありますので、それを利用して複数回復習をし長期間、授業で習ったことを覚えている状態をつくるという作戦を講じるのがポイントです。
・コミュニケーションをしっかりととることが生徒との信頼関係を築く上で重要だと考えます。授業は個別指導の特性を活かして、双方向のやり取りを非常に重要視していますが、その中での会話から生徒さんの関心や考えていることを引き出し、適切な指導やアドバイスができるように心がけています。またそのような会話の中から生徒さんが悩んでいることや困っていることなども知ることができます。生徒さんのことを考え、コミュニケーションを取ろうとする姿勢が自ずと生徒さんの心を開かせるのだと信じております。
私は「受験の枠組みを超えた一生モノの学びを提供できる時間」を目指して授業に臨むようにしています。志望校合格は、生徒さんの目標や夢を叶える通過点でしかありません。まさに「急がば回れ」で、そのように考えることが希望の進路=第1志望校(「行ける」ではない「行くべき」大学・学校)を叶える最短距離でもあると私は考えます。なりたい自分になるためにどのような努力が必要かを一緒にとことん考えていきましょう。授業の中ではそのために将来を見据えて様々なことを考えてもらう場面も多く設けます。大学生という立場からも大学での学びや大学はどういうところかということもお話しできたらと考えています。学校や塾、予備校の教員・講師よりも歳が近い分、相談にも大いにのります。私は授業はもちろん、授業や家庭での自分の学びに、そして自分の成長に満足感を持ってもらえるように最大限、努力します。
私は現在、大学生ですが、将来的には英語学の研究者として活躍できたらと考えております。また英語科教育法の研究をしており、第2言語としての英語習得法について知見を深めています。社会人の講師ではありませんが、家庭教師としての経験もありますので、安心してお任せください。
生徒の皆さんの夢や目標を、全力で応援します。そして皆さんの想いに応えるべく魂を込めて授業をします。
------------------------
以下に私の指導方針がよくわかる「家庭教師Q&A集」をまとめました。
【質問1】「7÷3」が分からない小学生がいます。あなたはどのように教えますか?
「7 ÷ 3」が分からない小学生には、言葉・絵・具体物を使って、「割り算」の意味と「割り切れない場合」の考え方を感覚的に理解させることが大切です。以下のように段階を踏んで教えます。ブロックやおはじき、絵などを使って実際に分けてみます。
【ステップ1】計算式の意味の説明
7個の丸やブロックを用意し、3つの箱に1個ずつ順番に入れていきます。2周(=1人2個)配ると、6個使って、1個あまることが目で見てわかります。よって「だから、7÷3 は 2 あまり1なんだよ」と説明します。
【ステップ2】計算式の書き方と答え方の説明
その次に式の書き方と答え方を確認します。7 ÷ 3 =2 あまり 1」と答える形を教えます。「2人に2個ずつあげて、あと1個だけ残った」など、状況にあわせて自然な言葉で説明してもらいます。
【質問2】「家庭教師」と「塾」の指導方法の最大の違いは何だと思いますか?
家庭教師と塾の指導方法にはさまざまな違いがありますが、最大の違いは、指導が「生徒一人ひとりに完全に最適化されているかどうか」という点にあると考えます。すなわち、家庭教師では「個別最適化された指導」が可能であり、塾では「集団最適化された指導」が主となるという違いです。
まず、家庭教師はマンツーマンの指導が基本であり、生徒の理解度・性格・学習ペース・生活リズムなど、あらゆる個別の事情に応じて授業を柔軟に構築できます。たとえば、ある生徒が分数の理解に苦しんでいれば、その単元に多くの時間をかけ、具体物や図を使って根本から丁寧に解説することができます。反対に、すでに理解が十分な単元はスピードを上げて進め、時間を有効に使うことも可能です。授業の進度・方法・使用教材などすべてがカスタマイズできるため、常に「その生徒のためだけの授業」を実現できるのが家庭教師の強みです。
一方で塾の授業は、複数の生徒に対して一斉に行われることが多く、あらかじめ決められたカリキュラムや進度に従って授業が進みます。そのため、すでに理解している生徒には退屈に感じられることがあり、反対に理解が追いつかない生徒には置いていかれる可能性もあります。もちろん、最近では個別指導型の塾も増えていますが、それでもなお「複数の生徒の中の一人」として扱われる性質がある以上、「完全に個に最適化された指導」には限界があります。
さらに、家庭教師は家庭というリラックスした環境の中で、生徒の集中力や心理的な安心感を高めやすいという点でも有利です。授業中の雑談や対話を通じて、生徒の関心やモチベーションに直接働きかけることができ、学習習慣の改善や自己管理能力の育成といった、学力以外の面にも寄り添った支援が可能です。塾でも信頼関係は築かれますが、教師1人あたりの担当生徒が多いため、個々の背景や日々の変化に細やかに対応することは難しいのが実情です。
以上のように、家庭教師と塾の最大の違いは、指導の「個別最適化」の度合いにあるといえます。家庭教師は、教える内容・方法・進度すべてをその生徒のために最適化できる点で、きめ細かく柔軟な指導が可能です。この違いこそが、両者の最も本質的な相違点だと考えます。
【質問3】集中力の持続しない生徒を指導する際に気をつけることはなんですか?
集中力の持続しない生徒を指導する際に気をつけるべきことは、生徒の特性に寄り添いながら、適切な学習環境と指導の工夫を取り入れることで、自然と学習への意欲や集中力が高まるように導くことです。そのためには以下の三つの観点が特に重要です。
第一に、指導内容や学習の進め方を生徒の集中力のリズムに合わせて調整することが大切です。長時間にわたって同じ形式の問題を繰り返すのではなく、適度に切り替えを取り入れることで飽きを防ぎます。例えば、問題演習の合間にミニクイズや雑談をはさむことで、生徒の気分をリフレッシュさせることができます。また、集中が切れやすい生徒には、一度の指導時間を短く区切り、「これが終わったら少し休憩」などと具体的なゴールを示すことで、集中しやすくなります。
第二に、生徒自身が自分の集中力の状態を意識できるような対話を心がけます。単に「集中しなさい」と注意するのではなく、「いまちょっと疲れてきたかな」「どこまでなら集中できそうかな」などと声をかけることで、自分の状態に気づき、自らコントロールしようとする姿勢を育むことができます。これは、将来的に自律的な学習習慣を身につけるうえでも非常に重要です。
第三に、生徒が興味を持ちやすい話題や教材を積極的に取り入れ、学習そのものに対する関心を高める工夫が求められます。例えば、英語の授業であれば生徒の好きなアニメやゲームに関連する英文を使ってみたり、国語であれば生徒の興味関心に近いテーマの文章を扱うことで、自然と前のめりに学習に取り組む姿勢を引き出すことができます。このような工夫は、学びに対するポジティブな感情を育てるとともに、集中力の持続にもつながっていきます。
以上のように、集中力の持続しない生徒を指導する際には、指導内容の構成、生徒との対話、そして教材の工夫という三つの柱を意識することが重要です。その生徒にとって無理のない形で「できた」「わかった」という成功体験を積み重ねられるような授業を目指すことが、集中力の向上ひいては学力の向上につながると考えております。
【質問4】勉強の習慣が身についていない生徒を、習慣づけるための工夫を教えて下さい。
勉強の習慣が身についていない生徒に対しては、まず「学習とは特別な行為ではなく、日常の中に自然に組み込まれるべきものである」という意識を育てることが重要でございます。そのためには、生徒の生活リズムや性格を踏まえたうえで、段階的に無理のない習慣化のための工夫を施すことが必要です。
第一に、学習のハードルを下げることが習慣化の第一歩であると考えます。いきなり一時間机に向かわせようとするのではなく、最初は五分でも十問でもよいので、「とりあえず今日の分はここまで」といったように、達成可能な小さな目標を提示いたします。そのうえで、取り組めたことに対してはしっかりと承認し、自信と成功体験を与えることが肝要です。このようにして、「できた」「続けられた」という実感が、次の学習へとつながる動機づけとなります。
第二に、学習の時間や場所を一定に保つことも効果的でございます。人間の行動は環境に大きく左右されるため、たとえば「毎日夕食後の二十分は勉強の時間にする」あるいは「学校の帰宅後に必ず机に向かう」というように、日常の中に学習を定着させる時間帯を設定いたします。これは学習に対する心理的準備を促すと同時に、生活のリズムに学習を組み込む効果がございます。
第三に、学習計画や記録の仕組みを取り入れることも有効でございます。私の指導では、日々の学習内容や時間を記録するシートを用い、どのような学びを積み重ねてきたのかを可視化しております。この記録は生徒本人にも、保護者にも共有することで、家庭での協力体制を強化し、学習への意識を高める助けとなります。また、一定の期間ごとに計画と達成状況を見直し、必要に応じて調整することで、学習習慣の定着をより確かなものといたします。
最後に、生徒とのコミュニケーションを通じて、「なぜ学ぶのか」「どのような目標のために勉強するのか」を対話的に確認することも大切でございます。勉強が単なる義務ではなく、将来の目標や自己実現につながるという実感が持てれば、学習はより自発的なものとなり、習慣化も容易になります。
以上のように、学習習慣の定着には、心理的な負担を軽減し、生活の中に自然と学習が溶け込むような環境と仕組みを整えることが重要であると考えております。指導者は、生徒の個性や状況を尊重しながら、共に試行錯誤する伴走者として寄り添っていくことが求められます。
【質問5】生徒が「何のために勉強をするのか分からない」と言っています。あなたは何と言いますか?
生徒が「何のために勉強をするのか分からない」と言うとき、その背景には勉強が単なる義務や苦痛に感じられていることが少なくありません。私はこの問いに対して、正面から丁寧に向き合うことを大切にしております。勉強の意味は一人ひとりにとって異なるからこそ、「君にとって、勉強が何の役に立ちそうか、一緒に考えてみようか」と問い返しながら、対話的に答えを見つけていくことが効果的です。
私はよく「勉強とは、将来の選択肢を増やすための準備なんだよ」と伝えています。将来、どんな職業に就きたいかがまだ分からなくても、自分にできることを少しでも広げておくことで、いざ選ぶ時に「選べる自分」でいられる。これはとても大きな財産です。何も知らずに人生を選ぶのではなく、知識や考える力を通して、自分で選び、自分で歩めるようになる。私はそのために勉強があるのだと伝えています。
また、私は「勉強とは、自分の世界を広げる旅でもある」とも話します。例えば、英語を学ぶことで海外の人と話すことができるようになる。歴史を学ぶことで、今の社会がどのようにできてきたのかを知ることができる。数学や理科を学ぶことで、自然や技術をより深く理解できる。こうした知識は、私たちの日常をより豊かに、そして意味あるものにしてくれます。
何より大切なのは、勉強を通じて「自分が分からなかったことを分かるようになった」という体験を積むことです。小さな「できた」が重なることで、「自分は学べる」という自信が芽生えます。この経験は、たとえ受験が終わったあとも、人生のあらゆる場面で「学ぶ姿勢」を支える土台になります。
このように、勉強の意味は決して一つではありません。私は生徒と一緒に、その生徒なりの「勉強する理由」を見つけていくことを大切にしています。そして、「今はまだ見つからなくてもいい、でも君が学んでいることには必ず意味がある」というメッセージを丁寧に伝えるようにしています。
【質問6】生徒との信頼関係を築く上で、最も大切なことは何だと思いますか?
生徒との信頼関係を築く上で、最も大切なことは「誠実に向き合い、対話を重ねる姿勢」だと私は考えています。どれほど指導技術に長けていても、生徒が心を開いてくれなければ、その力を十分に発揮することはできません。だからこそ、まずは「この先生なら安心して頼れる」「自分のことを理解しようとしてくれる」と感じてもらうことが最優先です。
そのために私が心がけているのは、生徒の話をよく聴き、その言葉の背景にある気持ちや思いに寄り添うことです。たとえば、生徒が「難しい」「できない」と言ったとき、それを単なる甘えとして受け取るのではなく、「何が難しいのか」「どこでつまずいているのか」を丁寧に探りながら、「そう感じるのは自然なことだよ」と受け止めてあげる。こうした小さな共感の積み重ねが、生徒の安心感につながっていきます。
また、私自身が「約束を守る」「言葉に責任を持つ」といった姿勢を貫くことも大切にしています。たとえば、次回の授業で扱う内容を予告したら必ず用意する、生徒の悩みに対して真摯に向き合い、必要であれば資料を用意する。こうした誠実さは言葉よりも行動を通して伝わるものであり、生徒はその姿を見て、「この先生は本気で自分のことを考えてくれている」と感じてくれます。
さらに、生徒が自分の力で成長したことを見逃さず、きちんと言葉にして認めることも信頼関係には欠かせません。努力や成果を適切に評価することで、生徒は「この先生に見てもらえている」という実感を持ちます。そしてそれが、さらに努力するための原動力にもなるのです。
このように、信頼関係とは一朝一夕に築かれるものではありません。日々のやり取りの中で、互いに誠実であること、相手の話をよく聴くこと、そして結果だけでなくプロセスを大切にする姿勢が、少しずつ絆を育てていくのだと思います。私は、家庭教師としての指導力以上に、この信頼関係こそが、生徒の成長を支える最も大切な基盤だと確信しております。
【質問7】自分がこれまでしっかり勉強をしてきてよかったと思うことは何ですか?
私がこれまでしっかりと勉強してきてよかったと心から思うことは、自らの好奇心を満たし、知的な世界を深く探求できる「自由」を得られたことです。現在、私は英語学・認知言語学を専門に研究しており、言葉がどのように意味を生み、人間の思考と結びついているのかを探る日々を送っています。その過程で得られる発見は、単なる知識の積み重ねではなく、自分の視野や世界の捉え方そのものを豊かにしてくれるものです。
たとえば、ある英文構造の背景にある理論を読み解いたときや、学生時代に抱いていた疑問が文献を通じて明らかになったときには、知的な興奮と喜びを感じます。これは、長年にわたって積み上げてきた知識と訓練があってこそ到達できた境地であり、勉強を継続してきたからこそ得られた贈り物のようなものだと感じています。
また、勉強を通じて身につけた論理的思考力や表現力は、学問の場だけでなく、日常生活や人間関係においても非常に役立っています。自分の考えを言葉にして伝える力、複雑な問題を丁寧に分解して考える力は、勉強を通じて磨かれたかけがえのない力です。
さらに、私はこれまでの学びを通して、自分が誰かの役に立てることにも喜びを見出せるようになりました。家庭教師として生徒の指導にあたるなかで、かつての自分と重なるような迷いや苦手意識を持つ生徒に出会うたび、「勉強してきてよかった」と実感します。なぜなら、その生徒の疑問や不安に対して、知識や経験をもとに応えることができるからです。
知識とは、自己実現のための道具であると同時に、他者を支える力にもなり得るのだということを、私は今の研究生活と指導を通じて強く感じています。だからこそ、学ぶことは単なる受験対策を超えた、「人生を豊かにする手段」であると信じています。
【質問8】あなたのこれまでの人生における大きな失敗と、そこから学んだことを教えてください。
私のこれまでの人生における大きな失敗は、大学入学当初、自分の「得意」や「関心」に固執しすぎた結果、学びの幅を狭めてしまったことでございます。具体的には、私は言語に対する強い関心から英語学・認知言語学の分野に深くのめり込みましたが、当初は他の学問分野や異なる視点を積極的に取り入れる柔軟さを欠いておりました。そのため、自分の考えや仮説がうまくいかない場面に直面したときにも、「なぜうまくいかないのか」を他の視点から問い直すことができず、研究の停滞を経験しました。
しかしこの挫折を通じて、私は「学問は一つの視点にとどまっていては深まらない」ということを身をもって学びました。たとえば、認知言語学の概念を理解する際にも、心理学や哲学、歴史などの知見が驚くほど大きな助けになることがあります。逆に、自分が学んできた言語学の視点を他分野の問いに応用することで、より深い理解や新たな視座が得られることも多くあります。こうした気づきは、学際的な姿勢を持ち、異なる考えに耳を傾ける姿勢の大切さを私に教えてくれました。
この失敗から私が学んだ最も大切なことは、どのような専門性を追求するにせよ、他者の視点に対して開かれた姿勢を保ち続けることが、自らの探究をより深く豊かにするということです。失敗を経てようやく、学びは「知識を蓄えること」にとどまらず、「自らの考えを更新し続けること」だと実感するようになりました。現在はその反省を活かし、異分野との対話や学び直しにも積極的に取り組むようにしております。この柔軟さこそが、学び続ける者にとって最も重要な資質の一つであると、今では強く信じております。
この失敗は、私自身の学びの方向性に大きな影響を与えただけでなく、生徒に寄り添う指導者としての視点を持つための大切な教訓となりました。失敗を通して得たこの経験を、これから出会う生徒たちの学びの支えとして役立てていきたいと考えています。
【質問9】あなたが受験対策の指導で、自信を持っている学校名とその理由を教えてください。
私が受験対策の指導において特に自信を持っている学校は、国立大学では大阪大学および京都大学、私立大学では早稲田大学および慶應義塾大学です。理由として、まず自らが大阪大学に現役で合格・入学しており、記述試験を中心とした国公立大学入試に必要な論理的思考力や記述力、読解力について、自身の経験と指導経験を通じて体系的に理解していることが挙げられます。また、過去には私が指導した生徒が京都大学に合格した実績もあり、難関国立大学に求められる応用力・記述力の育成には強い自負を持っています。
一方、私立大学の入試においては、自ら早稲田大学や慶應義塾大学にも合格しており、英語や国語における速読力、語彙力、知識の正確性が問われる客観式問題への対応にも精通しております。特に、早慶レベルの英語に求められる高度な語法判断や構文解釈に関しては、言語学を専門とする私自身の知識を活かして、受験生に理論的かつ効率的な解法を提供できる点が強みです。
加えて、私は大学入試の出題傾向や大学ごとの特色について常に最新情報を収集し、それを授業に反映させております。過去問の分析を通して、各大学がどのような力を重視しているのかを把握し、生徒一人ひとりに合わせた戦略的な指導を行うよう努めています。
以上のように、自らの受験経験と指導実績、専門的知見を基に、国公立・私立問わず難関大学の受験指導には強い自信を持っております。受験は単なる知識量の勝負ではなく、「合格するための学び方」が問われる場です。その方法を的確に示すことこそ、私の指導の強みだと自負しております。
【質問10】あなたが受験生の頃、モチベーションを維持するために工夫したことを教えてください。
私が受験生の頃、モチベーションを維持するために意識していたのは、「日々の学習に小さな達成感を見いだすこと」と「将来の自分を具体的に想像すること」でした。受験勉強は長期戦であり、時には疲れや不安に押しつぶされそうになることもあります。そうした中で、目先の得点や模試の結果だけに一喜一憂するのではなく、「昨日よりも理解が深まった」「前回は解けなかった問題が解けた」といった小さな進歩に目を向けるよう心がけていました。
また、私は「自分が大学でどのような学問を学び、どのような生活を送りたいか」を想像し、その未来に向かって勉強しているのだという意識を常に持っていました。特に、志望校のオープンキャンパスに参加したり、大学の講義動画を視聴したりすることで、「この環境で学びたい」という思いが一層強まり、勉強への意欲を保つ原動力になりました。
さらに、学習計画を立てて日々の目標を明確にし、それを記録することで、自分の頑張りを「見える化」し、達成感を得やすくしていました。計画表にチェックを入れるたびに、「今日も一歩進めた」という実感が得られ、それが継続の力につながっていたのだと思います。
最後に、私は勉強以外の時間も大切にしていました。音楽を聴いたり、友人と短時間でも話したりすることで気分をリセットし、メリハリのある生活を送るように意識していました。勉強一辺倒になりすぎず、自分自身のバランスを保つことも、長期的にモチベーションを維持するためには不可欠な要素だと感じております。
このように、私にとって受験勉強は「忍耐」だけではなく、「自己理解」と「未来への期待」を育てる過程でした。今でもあの時の努力が、今の自分を支える大きな土台になっていると実感しております。
【質問11】個人契約(もしくは直接契約)ならではの良さを教えてください。
個人契約(または直接契約)の最大の魅力は、生徒一人ひとりに寄り添った柔軟かつ密な指導が可能である点にあります。塾や家庭教師センターを介した場合、どうしても授業内容や進度、使用教材などが組織の方針に従う形になりますが、個人契約では、完全に生徒の目標や個性に応じて授業をカスタマイズできる自由があります。私はこれまで、個人契約だからこそ実現できた丁寧な指導や、生徒・保護者との信頼関係に基づく深い学びの場を多く経験してきました。
また、個人契約では指導者と生徒・保護者の距離が近く、コミュニケーションが非常に取りやすいという利点もあります。進捗状況や理解度の共有、進路相談や勉強習慣に関する課題などについて、リアルタイムかつ細やかに対応することが可能です。たとえば、「今週は学校でこのような単元を習ったので、復習を中心にお願いしたい」「英語の読解が苦手なので構文解析に重点を置いてほしい」といった要望に、その日の授業からすぐ反映することができます。そうした迅速で柔軟な対応こそ、個人契約の強みだと考えております。
さらに、契約形態が直接的であることにより、料金体系や指導時間なども明確かつ透明で、双方が納得したうえで信頼関係を築くことができます。生徒の成績向上や志望校合格を「ともに目指すパートナー」として、より責任感と誠意をもって取り組むことができる点も、個人契約だからこその魅力です。
私は指導において、「生徒が自分に合った学び方を見つけ、成長していくプロセスに寄り添う」ことを大切にしています。そのためには、生徒ごとの特性や背景、学習の進度に合わせて柔軟に方針を調整できる個人契約という形態が最も適していると考えております。このような関係性の中でこそ、生徒は安心して質問ができ、間違いを恐れず主体的に学ぶことができるようになります。
以上の理由から、私は個人契約(あるいは直接契約)による指導を非常に価値あるものと考えており、これまでの指導経験の中でも、最も成果を出してきた形態であると実感しています。
【質問12】あなたの好きな言葉・座右の銘は何ですか?
私の座右の銘は「至誠にして動かざるもの、未だこれあらざるなり」です。これは幕末の思想家・吉田松陰の言葉であり、真心を尽くして誠実に行動すれば、必ず相手の心を動かすことができるという信念を表しています。教育や指導の場においても、この言葉は常に私の心にあります。
家庭教師として、生徒に何かを教える立場である以上、まず自分自身が誠実に、真摯に向き合う姿勢を持つことが大切だと考えています。生徒がつまずいているとき、悩んでいるとき、あるいは勉強に気が向かないときでさえ、決して責めたり見放したりせず、誠意をもって関わる姿勢を貫くこと。そのような姿勢が、やがて生徒の心を開かせ、自ら学ぼうとする原動力になっていくのだと、これまでの指導経験を通じて確信しています。
この言葉を胸に、今後も一人ひとりの生徒と誠実に向き合い、信頼を積み重ねながら、確かな学びの道をともに歩んでいきたいと考えております。
【質問13】苦手科目を克服するためのポイントを教えてください。
苦手科目を克服するための第一のポイントは、「なぜその科目が苦手なのか」を自分自身で分析し、原因を明確にすることです。単に「嫌い」「分からない」といった感情的な理由ではなく、「どの単元でつまずいているのか」「どのような問題形式が苦手なのか」といった具体的な視点を持つことが、克服への第一歩となります。私の指導では、まずその原因を一緒に探りながら、生徒の「分からない」を言語化してもらうことに注力します。
次に大切なのは、小さな成功体験を積み重ねることです。苦手意識の根底には「できなかった経験」があることが多いため、難しすぎない課題を用意し、正解したり、理解できたりした実感を生徒に持たせるように工夫します。「あ、分かった」「この問題ならできるかも」と思えるようになれば、その科目に対する拒否反応は徐々に和らいでいきます。
また、苦手科目こそ、学習の「順序」と「理解の筋道」が大切です。とくに数学や英語などの積み上げ型の科目では、前の単元の理解が不十分なまま先に進んでも、さらなる混乱を招くだけです。ですから、学び直しが必要な場合には、前の学年内容までさかのぼり、基礎から丁寧に復習するようにしています。
さらに、「その科目を学ぶ意味」や「面白さ」に触れることも、克服の助けになります。苦手意識の強い生徒ほど、「何のためにこれをやっているのか」が見えていないことが多いため、学問の背景や実生活とのつながりを紹介することで、興味や関心を引き出す工夫をしています。
以上のように、苦手科目の克服には、原因の特定、小さな成功体験の積み重ね、段階的な理解の積み上げ、そして意味づけと興味喚起という複合的なアプローチが必要です。私はそのすべてを意識しながら、生徒一人ひとりの状況に応じた丁寧な指導を行っております。
【質問14】あなたが勉強を教える際の、時給以外でのモチベーション(動機)があれば教えてください。
私が勉強を教える際の最大のモチベーションは、「生徒が何かを理解し、できるようになる瞬間に立ち会えること」そのものにあります。これは非常に純粋で、職業的な報酬を超えた深い満足感を伴うものです。生徒が「なるほど、そういうことか」と目を輝かせる瞬間や、「できるようになった」と自信を持って報告してくれる瞬間は、何にも代えがたい喜びです。私自身、学問の世界に身を置き、英語学や認知言語学を研究する中で、知的な探究がもたらす発見や驚きに常に魅了されてきました。その感覚を、生徒とともに共有し、伝えていくことが、何よりも大きな動機となっております。
また、生徒の成長に継続的に関われることにも大きな意義を感じています。学習の内容だけでなく、学び方や考え方そのものを育てることは、将来にわたって生徒の支えになる力を授ける営みです。短期的な得点の上昇だけでなく、生徒が将来、学問や仕事に前向きに取り組めるようになることを目指して指導を行っております。
さらに、私自身の学びにもつながる点も、大きなモチベーションです。教えることは自分の理解を再構築することであり、生徒からの質問に対してより良い説明を考える過程で、私自身の認知や言語に対する理解も深まっていきます。学ぶことと教えることが双方向に作用するこの関係性に、大きな魅力とやりがいを感じております。
このように、指導の現場では常に「人の知的な成長」に立ち会えること、そして「学びのよろこび」を分かち合えることこそが、私にとって時給以上の最も強い動機であり、指導に誠実に向き合い続けられる理由です。
【質問15】「分からないところが分からない」という生徒がいます。あなたはどのように対応しますか?
「分からないところが分からない」という生徒の状態は、決して珍しいものではなく、多くの学習者が経験する非常に自然な現象です。むしろ、そのように正直に自分の状態を言語化できることは、学びの出発点として非常に価値があると私は捉えています。そのような状況において、私がまず心がけるのは、生徒の不安を受け止め、「それは全く問題ないことだよ」と安心させることです。そのうえで、段階的かつ対話的に理解を整理する作業を共に行います。
第一に、生徒に負担のかからないレベルの基本問題からスタートし、「ここまでは分かる」と感じられる地点を一緒に探します。生徒の理解の輪郭を確かめ、安心して「分かる」と言える範囲を明確にすることによって、自信と見通しを持たせます。この際には、生徒の言葉を引き出すことを特に重視します。「どこから迷った?」「この言葉の意味は知っている?」などと問いかけ、自分の理解の整理を促します。
第二に、学習内容を視覚的に整理します。板書や図解、色分け、マッピングなどを活用し、複雑な内容を構造的に捉えられるように工夫します。特に英語の文法や数学の論理構造は、視覚的に表すことで飛躍的に理解しやすくなります。これにより、「何が分からなかったのか」が明確になりやすくなります。
第三に、「できた」「分かった」という小さな成功体験を積み重ねていきます。これにより、「私は何も分からない」という自己認識が徐々に変化し、「少しずつなら進めるかもしれない」という肯定的な学習意欲が芽生えてきます。このプロセスこそが、学びを支える土台になります。
最後に、何より大切なのは、生徒が安心して「分からない」と言える信頼関係を築くことです。私は授業の中で、生徒の発言を決して否定せず、どんな些細なつまずきにも丁寧に向き合います。その積み重ねが、やがて生徒自身の学びを主体的なものに変えていくと信じています。
【質問16】最後に生徒さんへのメッセージを!
志望校合格はゴールではなくて、夢や目標を叶える通過点であるはずです。受験という、つまらない枠組みを超えた、真の志を叶えるための一生モノの学びを提供します。皆さんの目標を全力で応援し共に走り抜けたいと思います。一緒に頑張りましょう!

たろ
なし~3000
在学 早稲田大学
男性
はじめまして、ご覧いただきありがとうございます。
私は、生徒のニーズに合わせた指導をすることが得意です。まず、生徒の現在のレベルや目標を理解するために時間をかけ、それに合わせた個別の計画を作成します。また、生徒が自信を持って問題に取り組めるよう、基礎的な知識を理解してもらうことを意識しています。指導時間だけではなく、日々の家庭学習をどのように進めていくかが成績を上げる重要なポイントになると考えているので、週や月単位での学習計画を一緒に立てていきます。
勉強のやる気を出してもらえるように、生徒とのコミュニケーションを大切にし、生徒が疑問や悩みを解消できるように常にオープンな態度で接することを心がけています。これまで家庭教師を2年間してきましたが、指導した生徒は自信を持って問題に取り組み、成績を上げることができました。
面談や体験授業をしていますので、お気軽にご相談ください。

Kenya
なし~2000
在学 横浜市立大学
男性
初めまして、プロフィール読んでいただきありがとうございます。
私自身医学部に入学してから7年間、医学部受験対策に関わってきました。父親も家庭教師をやっており、未来ある子どもたちの成長に携わることのできる家庭教師の仕事に興味があり、教師の仕事を始めました。
現在6年になりますが、北米への約半年の語学、医学英語留学の経験もあります。
その中で様々なタイプの生徒を指導し、特に物理数学に関しては指導時間それぞれ200時間を超えており学生ですがプロ並みの指導が可能であります。更には自分自身の受験経験をも活かして全力でバックアップします。
問題の解説等だけではなく、スケジューリングなども作成できます。実際に現役時代には時間単位でスケジューリングを組んでおりました。
さらに家庭教師をする上でご家庭様との連携は必須と考えておりますので、少なくとも1学期毎の面談と、毎授業ごとのレポートを作成しております。何かご不明点をご両親がお持ちになった場合でも迅速かつ的確なアドバイスや意見交換が可能です。
少し熱をもって指導する傾向にありますので、授業の終わりの時間が伸びてしまうこともしばしばあります。
そんな熱い指導をぜひとも体験授業にて肌で感じていただければなと思っております。現在ありがたいことに皆様からたくさんのご依頼を頂いている状況です。私と父親の2人体制での指導となることもあります。ご確認お願い致します。
最後になりますが、諦めずに勉強すること、これが一番大事です。自分の今の成績では無理だから、、、などと考える前に是非一度ご相談ください。合格までの最短経路を一緒に作り上げていきましょう。
ご利用の流れ
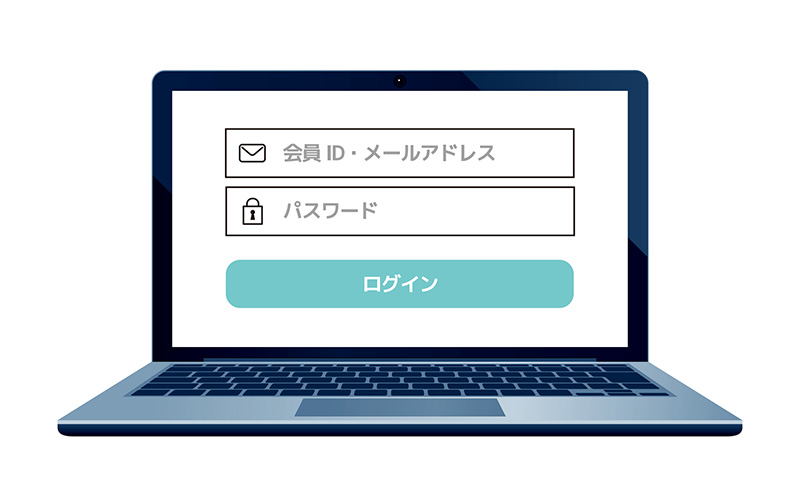
1.会員登録
カンタン登録で、サイトにログイン!

2.先生へオファー
「新着先生一覧」には素敵な先生ばかり♪先生は早い者勝ち!少しでも気になったら先生にすぐオファー♪
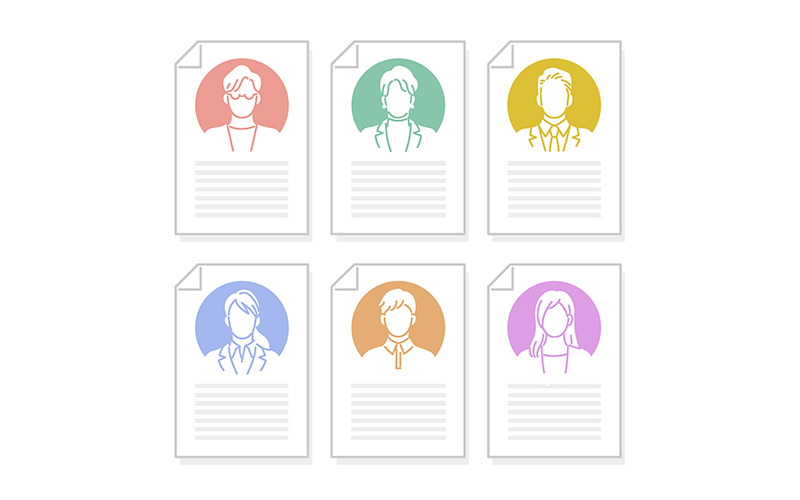
3.先生を集める
私に先生集まれ!先生を広く集めて、お望みの先生を選びましょう♪

4.紹介料支払い
メッセージで先生と面談日時・場所などを確定後、紹介料をお支払いください。

1.会員登録
高時給アルバイトへようこそ!
会員登録して、サイトに即ログイン!

2.プロフィール登録
会員登録後、すぐにプロフィール登録!能力やスキルをPRしましょう!プロフを見た方から即オファーがあるかも!?

3.生徒へ応募
毎日更新される新着生徒一覧♪教えたい生徒に応募して猛アピール!指名&高時給をGETしましょう!

4.面談&授業スタート♪
生徒と連絡・面談し、無事に契約が決まったら授業スタート!授業料は全て先生のもの!